季節の変わり目、体と心を休ませる時
こんにちは、40代独身フリーランスのユキマツリワラコです。
季節の変わり目、なんとなく体も心も調子が出ない……そんなふうに感じていませんか?
朝晩が冷えるこの時期、体の変化を感じる方も多いのではないでしょうか。
寒さを防いで体を温めることはもちろん大切ですが、それ以上に大切なのは「自分を休ませてあげること」かもしれません。
今回は、すきさん著『ゆるませ養生』から学んだ
“頑張っていなくても休む”
をテーマに、体と心をいたわるヒントをお届けします。
去年までの私は「頑張りすぎて休めない人」
私は、今でこそ毎日元気に過ごしていますが、去年までの私はまさに「頑張りすぎて休めない人」。
仕事が一段落するたびに、ひどい風邪を引いて寝込んだり、胃腸炎になったりと、体調不良を繰り返していました。
「この体調不良はなんなのだろう?」「これはどうにかしないと…」
そんな状況に陥っていた去年の今ごろ、私を救ってくれたのがこの本でした。
「休み方」を知らない私たち

今回ご紹介するのは、すきさん著『ゆるませ養生』(大和書房、2021)。
京都にあるお灸と養生の専門治療院「お灸堂」の院長、すきさん こと 鋤柄誉啓(すきからたかあき)さんが「養生」=「自分を大事にする作法」について書かれた一冊です。
何かと頑張りすぎている私たち。「頑張る」の対になるのが「養う(養生)」。
なのに、私たちは「頑張り方」は知っているけど、「休み方」を知らない。
その「頑張りグセ」を「養いグセ」に変えていきましょう、とすきさんは呼びかけます。
本書では、養生のコツや、「温める養生」「眠る養生」「触れる養生」「動く養生」など、頑張りすぎてしまった体へのさまざまな養生が紹介されています。
紹介されている「温める養生」や「触れる養生」などを取り入れると、周期的な体調不良は激減!
私を救ってくれたこの本には、本当に感謝です。
前回ご紹介した「体を温める小さな習慣」も、この本から学んだことがたくさん生かされています。
「頑張っていなくても休む」という考え方に出会って
もう一つ、この本から学んだ大きなことがあります。
それは、「頑張っていなくても休む」という考え方です。
すきさんは、「動いてから休む」ではなくて「休むから動ける」という考え方が本来であり、本当に疲れて余力がなくなると体は上手に休めないのだと説いて、次のように読者に語りかけてくれます。
頑張っていなくても休む、
成果が出ていなくても休む、
病気になっていなくても休む。
これからは、これくらいの感覚でいきませんか。
(同書、pp.101–102/太字は原文)
これは、私にとっては目からウロコの言葉でした。
休むことへの罪悪感に気づいた瞬間
すきさんは、多くの人が休むことへの罪悪感から「成果を出したら休んでいい」「病気になってしまったら休んでもいい」と思っているのではないかと書いています。
何を隠そう、私もそんなふうに思っていた一人でした。
休むことは、まるでご褒美。何かできたら与えられるもの。
そう思い込んでいた私にとって「頑張っていなくても休む」という考え方は、とても衝撃的でした。
振り返ってみると、「休むことは悪いこと」と、休むことへの罪悪感を強く持っていた自分に気づきました。
確かに私は、ひとつのプロジェクトが始まると、終わるまで休んではいけないような気持ちになり、少しでも休むと悪いことをしたような気分になっていました。
周りにバレないように(という感覚でした)休みながら、その分を取り戻さなくてはと、いつも以上に頑張って挽回しようと常に頑張る。
しかも、休んでいる時にも罪悪感があるので、仕事のことが心から離れず、本当の意味で休めていません。
そして、まともに休むことなく体力を削りながら頑張り続け、プロジェクトが終わった頃には眠る体力もないほど疲れ切り、体調を崩して病気になる、ということを繰り返していたのです。
よく考えれば、休まずに仕事をし続けるなんて無理に決まっています。
ですが、一つのプロジェクトを完遂できたら=「成果を出せたら」休んでもいいと無意識に思っていた私は、つまるところ、「成果を出すまで休んではいけない」、成果を出せていないなら「病気になるまで休んではいけない」と自分で自分を追い込み、無理をさせていたようなものでした。
そう、自分を苦しめていたのは、仕事そのものでも、他の誰でもなく、この自分だったのです。
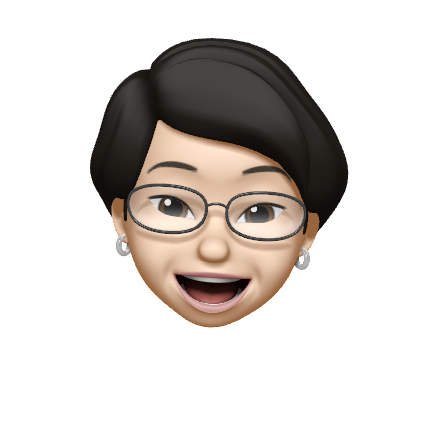
ちなみに、仕事仲間のワラオは上手に休む天才です!
休むことは悪いことじゃない——自分の考え方を変えた3つの実践
「このままだと一生、病気を繰り返してしまう!」
「休むことは悪いこと」という思い込みを持っているかぎり、この負のループから抜け出せない。
初めて危機感を持った私は、少しずつでも自分の考え方を変えていくことに決めました。
① 自分の認識を上書きする
私はまず、これまでの自分の行動や、その時の感情を思い出し、確認しながら、
「このプロジェクトの途中で休んだのって悪いことだった?」→「悪くなかった」
「取り返そうとして無理に頑張る必要あったかな?」→「なかった!」
と、こんな感じで、ひとつひとつを「そうじゃなかったよね」と自分に言い聞かせました。
自分の考えを上書きし、これまでの認識を変えていく作業です。
② 疲れ切る前にちょこちょこ休む
それから、現在進行中の仕事でも「ちょっと疲れてきたかも。休むことは悪くないよ。ちょっと休んでおこうか」と自分に声をかけて、疲れ切る前に休むようにしました。
そして、休む時には、なるべく仕事のことは考えない。
半日ほどでもしっかり休んでリフレッシュし、意識的にメリハリをつけて仕事をするようにして、疲れ切る前にちょこちょこ休みながら仕事をするように変えていきました。
③ 限界まで頑張らない
もう一つ気をつけるようにしたのは、限界まで頑張らないこと。
限界まで頑張ってしまったら、休む体力もなくなり、いわば手遅れの状態。
今までそれが100パーセントの頑張りだと思っていたけれど、実際には、120パーセント以上だったかもしれません。
その日の仕事を終える時、「まだ頑張れそうだけど、今日はここまでにしておこう」と自分の思う70%くらいのところでやめておく。
そうすれば、その日は余力を残して終わることができ、夜もしっかり眠れて、翌朝また元気に仕事を始めることができます。
最初は「こんなんでいいのかな?」という感じでしたが、仕事にまったく支障はなく、むしろ効率よく捗るようになりました。
- 自分の認識を上書きする
- 疲れ切る前にちょこちょこ休む
- 限界まで頑張らない
自分の認識を変えるのは少し時間がかかりましたが、「休むから動ける」「頑張っていなくても休む」を意識して、今ではメリハリをつけて、仕事と上手に付き合えるようになりました。
まとめ——私たちは思っている以上に、もう十分頑張っている
すきさんの言うように、私たちは思っている以上に、もう十分頑張っています。
「休むから動ける」。
そして、「頑張っていなくても休む」。
休むことは、サボることでも、ご褒美でもなく、自分を整えるための、ほんの小さな“養生”です。
私もようやく、ちゃんと休めるようになって、毎日が少しずつ穏やかになりました。
忙しい日々の中でも、ひと息つく時間を持てたら、それがきっと、自分をやさしく生かす力になると思います。
「頑張っていなくても休む」。
頑張りすぎているみなさん、今日も、どうか安心して休んでくださいね。
次回予告
次回は、ちょっと息抜き。私の部屋に住んでいる「小さな鳥ちゃん」たちをご紹介したいと思います🕊️
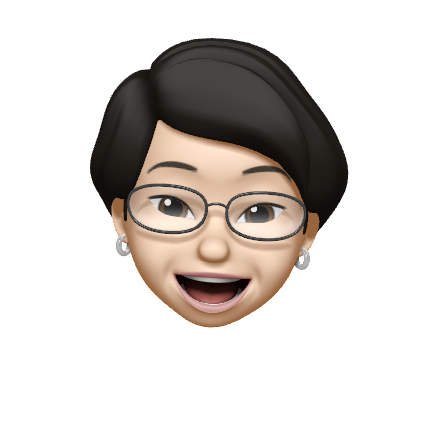
「読書からの学び」シリーズはこちらから▼
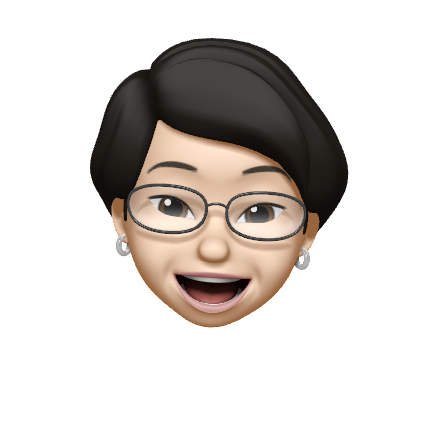
「やさしく生きていくためのヒント」シリーズもぜひどうぞ!▼
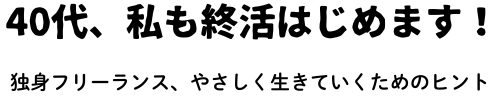
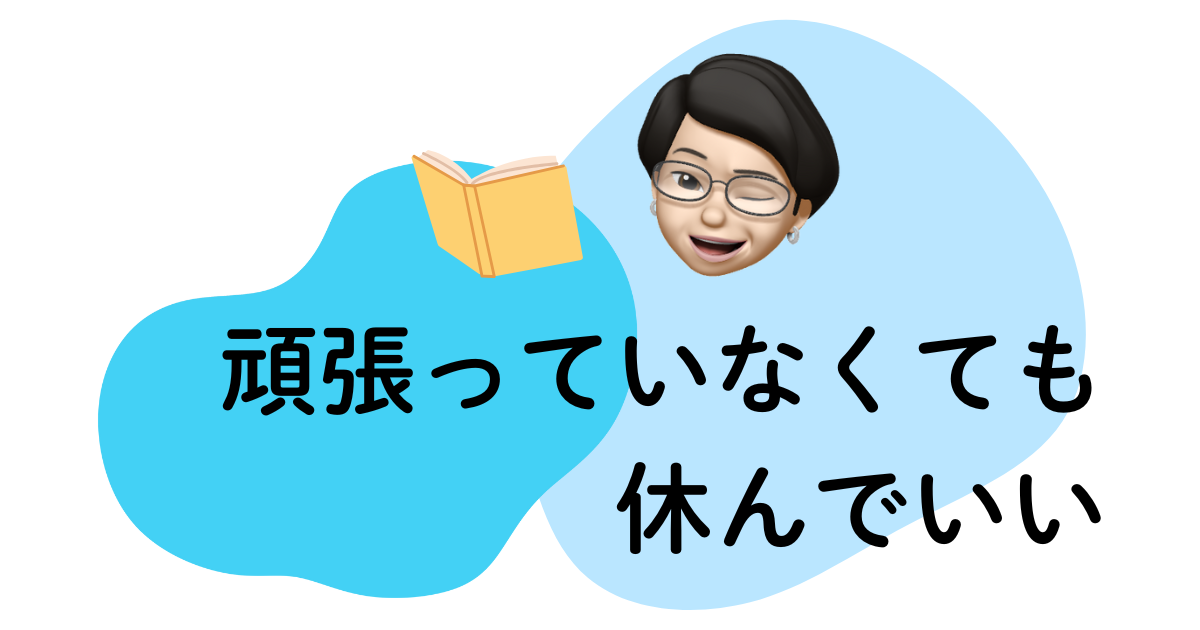
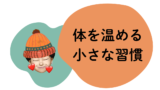
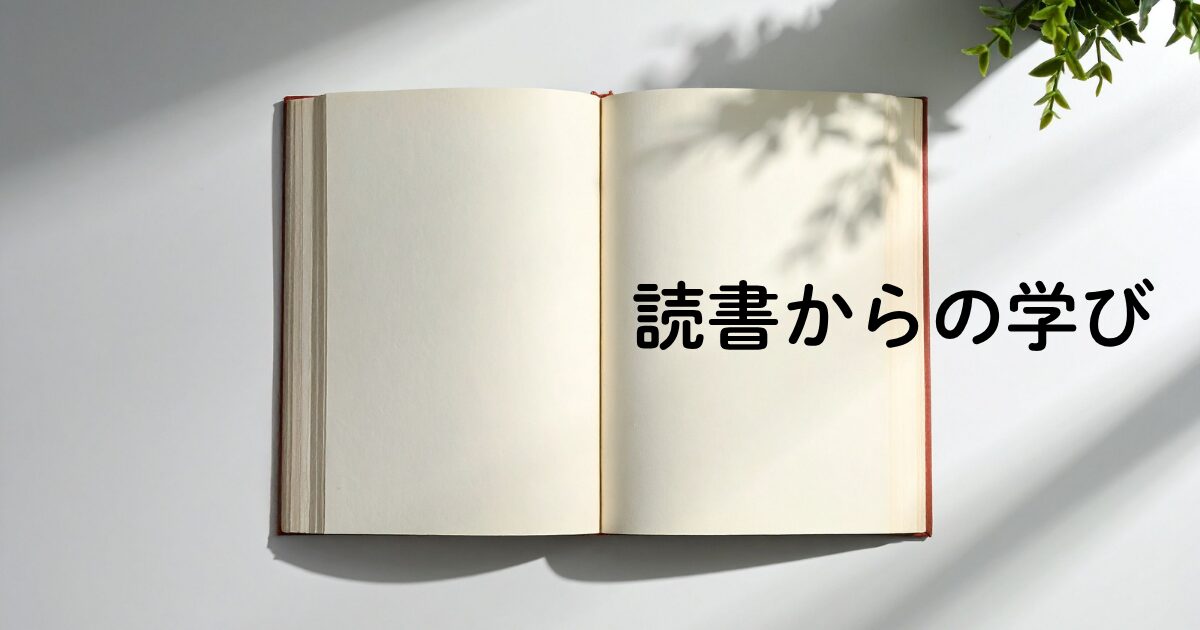
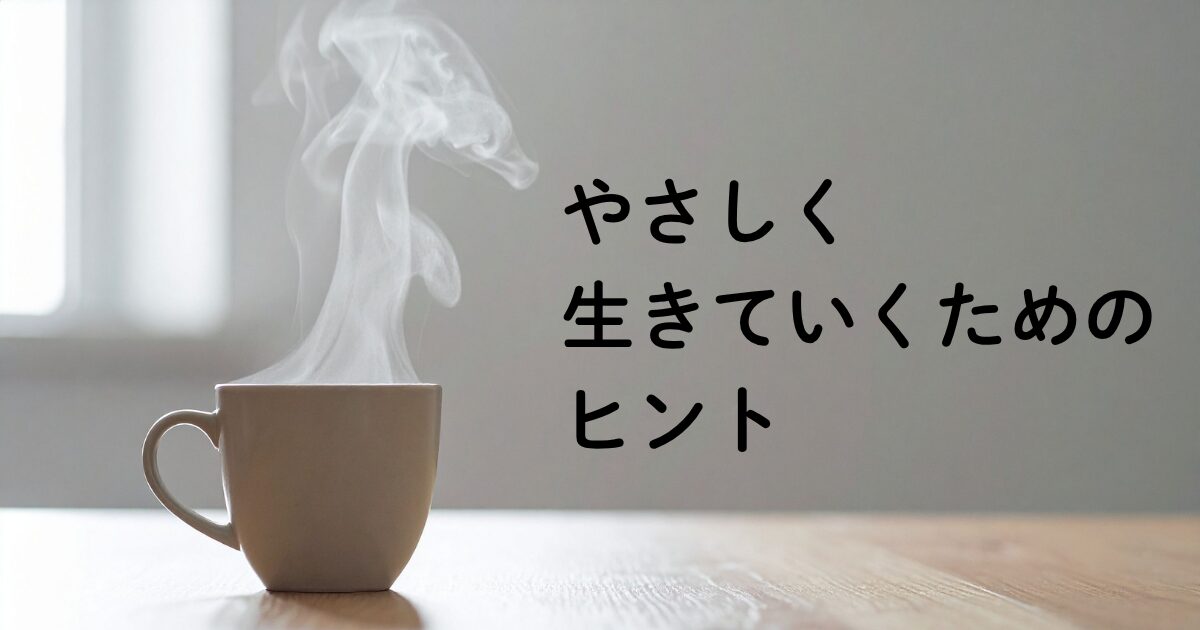
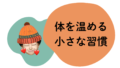
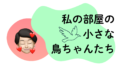
コメント